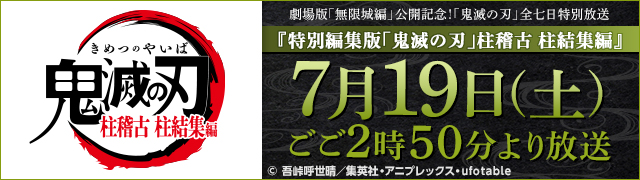番組審議会から(第626回)
番組審議会から(第626回)
第626回番組審議会
| 議題 | 『withコロナ時代に、地上波テレビ放送とテレビ西日本に望むこと』 |
|---|---|
| 出席委員 | 藤 井 克 已 委員長 進 藤 卓 也 副委員長 石 村 一 枝 委員 喜多村 浩 司 委員 舘 賢 治 委員 森 弘 亨 委員 田 中 徹 委員 林 田 歩 委員 |
| 欠席委員 | 伊 藤 真奈美 委員(レポート) 中 村 ク ミ 委員(レポート) |
感染を予防しながら日常生活を送ることが当たり前となった「withコロナ時代」。収まりつつあった新規感染者数は、冬の寒さ到来とともに再び増加傾向となるなど、感染状況は日々変化しており、感染者数増加や大勢人が集まる場所への外出に対して、7割強の方が依然として不安を持っているとの調査結果も出ています。
一方で、徐々に経済活動を戻していくことも重要な課題となっています。
また、放送業界では、5G時代を見据えた新しいスポーツ中継「リモートプロダクション(コロナ禍においての密回避のため、試合会場のカメラ映像を全て本社に伝送し、中継車内で行っていた制作作業を全て本社にて行うもの)」など、これまでにない取組みも始まっています。
このような状況を踏まえ、今回は上記テーマについて、番組審議委員の皆様から、自由闊達に忌憚のないご意見を頂戴する審議会としました。
委員からは
- 感染防止に関するものは大変重要な情報なので、TVはネット系情報でバズっているものに対してチェックを入れてほしいと思います。大きな話題になるものほど裏を取ってほしいです。
- 暗い話題ばかりを放送していると経済は確実に冷え込むと思います。明るい話題を必死で探して意識して流すことが大切と感じます。
- エッセンシャルワーカーに関しての差別については、「医療従事者に対する偏見差別のために医療従事者数が減り、あなたが罹患したときに治療が受けられない日が来るかもしれない」ということを繰り返し伝えることだと思う。
- どのチャンネルもコロナ一色だなと。しかも同じ顔ぶれが結構好き放題に話している気もします。何かのデータに基づいてとか、きちっとしたバックボーンがない人たちが感情論的に話していて、視聴者は、何が事実で、何を信じてよいかが分からない。
- テレビは世論を作ってきたわけですよね。下手すると、戦争を起こしたり左右するような影響力を持っていますけど、若い世代はネット文化で、テレビを見ないという事実がある。その最たるものが、民主主義国家、最先端の国と言われているアメリカの大統領選で、SNSで世論が作られて、結局、国民の分裂まで起こりつつあるという現実です。これが島国である日本で起こらないかというと、その保証は何もないわけなので、まさに報道の力の真価が問われているのではないかと日頃感じています。
- 感染者やエッセンシャルワーカーへの偏見とか差別をなくすためにということですが、コロナとは関係なく、我々人間の世界には今までにも偏見や差別があったわけで、今さら感があって、結局コロナでは報道があおっているのではないかと。正確かつ適切に報道するというところは非常に注意すべきことではないかと感じます。
- 総広告費は分母が大きくなっていて、それをインターネットが取っているというのは事実ですけれども、地上波のほうもしっかりキープされているのではないかと思うので、取り戻すというよりも共存していくことを考えるべきではないかなと。
- 専門家の意見を切り取ったり演出をしたり、それから一方的な見解を紹介するというのが最近非常に気になっています。こういった放送というのは視聴者の不安をあおりますし、誤解に基づく偏見にもつながるので、ぜひそういった悪影響があるということを再認識してほしいと思います。
- インフルエンザとか、ほかの疾病の感染数、死亡者数がコロナの時代にどうなっているのかとか、交通事故、犯罪数、自殺者数といった社会生活や経済に関する客観的な事実と関連付けて発信することで、視聴者の方が、この社会が変わっているんだということ、それから、withコロナの時代にどう生活していくべきかということを考えるきっかけにできればよりいいのではないかと思っています。
- 昨年の2月3月ぐらいから、自分の人生でこれほどテレビを見たことはないなと。やっぱり地上波のテレビのライフラインとしての情報発信機能というのは非常にあるなと感じました。
- 情報の信頼度というのも、誰が発信したか分からないネットに比べて、テレビ局という存在があるから高いのかなと思っています。特にネットがなかなか使いづらい方に対しては、リモコンのスイッチを押すだけで気軽に情報が得られるテレビの優位性というのを、ネットに押されているから何となく卑屈になられているのかもしれませんが、ここはもうちょっと自信を持ってもいいのではないかと思います。
- 定量的なデータが非常に不足していると感じています。緊急事態宣言で、家賃の補助金が外食の大手と中小で差があると出ていますけれども、では、もともとどういう利益構造で、賃料の負担や人件費がこれぐらいあって、その何万円をもらうことにどれぐらいのインパクトがあるのかということを知りたいなと思います。
- コロナ禍報道の1年だったんですけれども、正直に申し上げて、非常に不満足な内容だったと言わざるを得ません。しかもこれは全ての放送局に対しての感想であります。テレビ放送がこんなにも役立たないメディアだったのかと愕然とする思いで毎日見ておりました。
- 未知のウイルスに対応するんですから、何をどうすればよいのかということは誰にも正解が分からない。ですから、試行錯誤の連続の中から一つずつ解を導き出してウイルス撲滅につなげるしかない。そんなときに政府や自治体の対策を一方的に非難したり政争の具にするやからに力を貸すようなマスコミ、ジャーナリズムは、国民に敵対する存在にすぎなくなってしまうし、そうなりつつあると思う。今は国民も一致団結してこの災禍に立ち向かうときだということを明確に出すべきだ。
- 国家政治と国民生活をリアルタイムに、しかも相互通行で、インタラクティブにつなぐ役割を果たすことは、テレビメディアに課せられた使命だと覚悟すべきですし、そういう動き方をすべきだと思う。
- 国民に何を伝え、国に何を伝え、お互いに一緒になってこの国家を守ることができるか。その役割を果たせるのはネットではなくテレビ媒体だと、今こそジャーナリズムが強大な力を発揮できるときだと思うんです。だから、これはテレビが変われる最大のチャンスだと捉えて行動すべきだ。
- テレビではいろいろと大きい話を言っています。現実はこういう状況だという不安におののくばかりの情報だらけですが、身近な本当に小さな情報をテレビの片隅にいつも載せて発信していただくと、とてもありがたいと思います。
- テレビというのは、やっぱり目で見て美しくて、特に女性は、髪形を見たり、所作を見たり、情緒を見たり、ファッションを見たり、本当に息づかいを感じるものなんですね。経済には文化や美が絶対に必要なので、テレビというのは絶対になくならない。そういうものをもっと発信してもらいたい。
- 検査数とか陽性率は母数が日によって違いますので、率で公表する場合は本当に気をつけていただかないといけない。雪の影響がありましたとか、天気によって人の出は変わってきますので、数字は正しく出していても、適正かどうかというのは、そういうところをきちっとコメントした上で視聴者が判断できるようにしないといけない。
- ラジオは何か一つの音声を流していれば副音声というのはあり得ないわけで、そういう意味で、マルチで情報を伝えられるテレビというのは、誰が見ているかわからないけど、とにかく情報を伝える、流すということが一つの使命として大きな安心性に結びつくのではないかと期待しているところです。
- TNCを初めとする地上波テレビ局が発信しているものは、市民や住民から見れば、それだけの組織力を持って、きちんと取材して、あるいは、きちんと考えて番組を作ってその上で流しているという信頼感を、実はネットの世界にいる人も知っているのではないか。したがって、大きな影響力を発揮するのはテレビのほうではないかと思っていますので、その点は自信を持っていただきたい。
- 価値観が変わって、それぞれに正義を持っているんだと言うゆとりがなくなって、俺が正義だという思い込みが非常に強くなっているように思います。これを中和させ、気づかせるのはやっぱり大きなメディアだと感じています。
- 社会の大部分を包容できるような立場がどこにあるのか、お店はどうなのか、考え方はどうなのか、そういうことを局自身が独自に判断して、英断を持って流していっていいのではないかと思います。
- 地域密着型のテレビ局を目指すことだと思います。地元のことならどんな小さなことでも情報を伝えることのできるテレビ局であってほしいです。
- 人の気持ちに寄り添える共感型の人間味のあるキャラクター(演者)がもっと必要だと思います。
- 文化は変化してこそ価値あるものだと思います。これからは、人が大事に思うことや生活のニーズに寄り添って、また新しい文化を作り上げていかなければと思っています。テレビも文化の源です。地方に根付いたものを、地方の人のために、誇りを持ってこれからも数多に広めていかれることを切に願っております。
- 正確で信頼される情報を伝えていくためには、基本は三現主義だと思います。現場、現物、現実の三つをしっかりやることと、その行動に伴って、コンプライアンス、ガバナンスがしっかりできているかというのを確認しながらやっていく必要があるのではないかと感じています。
- ローカルの魅力や話題を適時的確にきちっと放送してほしいなと。『華丸・大吉のなんしようと?』が大好きで、いつも楽しく見ているんです。そこに絆もありますし、ローカルの魅力が非常にあると思いますので、そういうものにはぜひたくさんの制作費をスタッフに落としていただいて、面白い番組を作っていただければなと思います。
- TNCの番組では、コロナの情報を非常に細かに出されていていいなと思っているんですけれども、あともう一つ、withコロナ、afterコロナを見据えた生活をどうするのかといったところを視聴者の方が想起できるような情報も発信できたらいいなと思っています。
- 少子高齢化が進展して、地域の課題というのは非常に顕在化しています。特に九州では顕著になっていると思いますし、そこにコロナが追い打ちをかけて、産業界、特に観光・飲食業界は大ダメージを負っていると思います。テレビが持つ情報発信力という強みを生かして、地域の活性化や課題解決をぜひリードしていただきたいと思っています。
- 実際に取り組んでおられますけれども、ゴールデンの時間帯に局独自の制作番組を放送するといったことで、キー局に頼らない地域オリジナルの番組編成をもっと大胆にしていってもいいのではないかと思います。
- これからはいわば“サステナブル”ということがキーワードになってくるかと思います。地元ローカル局として生き残るためには、一般的にはミレニアル世代とかZ世代と言われますけれども、さらにはもっと若い20年後30年後の社会の主役になる世代の意見も取り入れて、番組制作や経営の舵取りを行っていくことも必要ではないかと思います。
- ステークホルダーが誰で、誰に対してどう応えていくかというのは、何をやるべきで何をやらないかを決めていくような話だと思いますので、実を言うと、社員だったり、取引先だったり、もしかしたらキー局のフジテレビだったり、九州各局だったり、いろんなところと議論していくテーマなのかなと思っております。
- TNCの夕方の番組は結構見ているんですけれども、ボードを使って非常に分かりやすいなということで、ぜひこの動きを続けていただきたいと思います。若干ナショナルの放送時間を減らしてでもローカルを増やしてもらったほうが、より落ち着くかなと思っています。
- これからはもっともっと地上波が大事になっていく時代で、もっと地域経済に貢献できるような番組を作ってほしい。例えば『うどんMAP』のような、岡澤君が一生懸命回ってくれて、うどん屋さんを活性化してくれていることは本当にありがたい。
- 正確かつ適切かというところについては、情報がどんどん変化するところで、数字で話す、ボード化するという形で、視聴者にも分かりやすくしているということでは説得力がすごくあると思います。だから、すごく改善されてきたなと感じております。
- 気軽に見られるというところでは、やっぱりネットでの見逃し配信をもっと増やす。例えば『ゴリパラ見聞録』は逆にネットを飲み込んでしまうぐらいの勢いで、YouTubeにもダーッと上げていただいていて、ああいうのは若者の登録者数も多いからよろしいかと、よくやっていただいていると思います。
- ローカル局の役割としては、単に報道するということから、地域を盛り上げて経済を活性化していくことが使命である。乗り越えよう新型コロナ、コロナからの復活をぜひホームページの中でもしていただいて、レシピなどの情報も得ながら、それをまた番組制作に生かしていくという形でグルグル回っていったらいいよねと感じているところであります。
- 例えば天神から博多駅へ行くときに地下鉄とバスはどちらが安全でしょうかとか、明日葬式があってJRで長崎に行かないといけないけど朝と昼と夜ではどこが一番安心・安全に行けますかみたいな、もう一つ下の生活レベルの情報を欲しているのではないか。
- FNNグループの力をぜひ発揮していただきたいということです。端的に言うと、他県ではこのようなコロナ対策の取り組みをやっていますとか、参考となるような事例、有意な取り組み等をどんどん紹介してもらいたい。逆に、福岡の情報も発信していただきたい。
- まさに家族で、子供からお年寄りまで安心して一つの番組を見られるというのが50年60年続いた要因の一つであると言われているみたいですので、こういう時代だからこそ、家族がまとまってテレビに向き合えるような番組をぜひ提供していただきたいと思います。
などの意見を頂きました。
局からは
- 新型コロナウイルスに関して正確かつ適切な情報をお届けするということ、少しでも有益な情報をより内容の濃いものとして放送することを心がけております。
- 新型コロナウイルスだけではなく、台風や集中豪雨、さらには大雪など、同様の対応を行っております。有事の際に頼りになる信頼のおけるテレビ局になることを目指しております。
- こんな時代だからこそ、エンターテインメント性の強い番組も制作するというものです。コロナ禍の折、どうしても気持ちが落ち込んだり、生活が苦しくなっていく中で、少しでも視聴者の皆さんの心を癒し、気持ちを前向きにする番組も放送していかなければならないと考えております。
- 報道部も連日、いろいろと批判はありましょうけれども、コロナ報道を続けております。この時期だからこそ、我々メディアの真価が問われるというのは身にしみて感じております。
- 一番重きを置いているのは生活者目線というか、困っている生活者がどのように動けばいいのかといったところを丁寧に報道することを心がけておりますが、まだまだ届いていないのかなと反省しております。
- 一つの大きなテーマである“触れ合い”みたいなものが今までどおりできなくなってきました。ただ、行くととても喜んでくれたり、本当に頑張っている皆さんの姿を少しでもお届けできたりするというところはあるので、感染対策をしっかりしながら、何か工夫をしながら番組制作を続けていきたいなという思いで続けております。
などの説明をしました。
番組審議会事務局より
- ご報告、ご説明事項
日本民間放送連盟が2020年12月9日付で作成した「「番組内で商品・サービスなどを取り扱う場合の考査上の留意事項」の周知・徹底について」をお配りし、当該文書が作成されるに至った経緯等を説明しました。
- 視聴者レスポンスについて
11月、12月に寄せられたご意見などの件数、および特徴的なものを書面にまとめてご報告しました。
過去の番組審議会
審議会 委員名簿
- 作成日
- 2021/01/28 15:14
- 最終更新日
- 2021/01/28 15:27